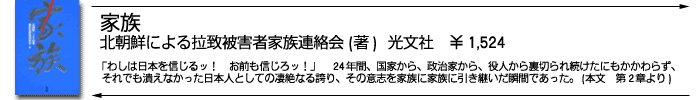|
|
||
| |
2003年8月1日創刊
|
||
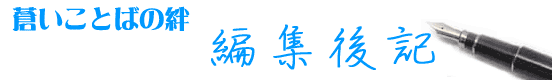 |
|||
| |
原稿依頼にまつわるエピソードや編集部員の独り言など編集後記の名を借りた雑談となるやも知れず。期待せず読まれんことを。 |
||
| |
|||
|
|||||||||
| 「不肖・宮嶋」。ひと呼んで「写真界のリーサルウェポン」。カメラマン「不肖・宮嶋」の名を一躍有名にしたスクープ写真を読者は覚えていらっしゃるだろうか。いや、それはもちろんリクルートの江副社長(当時)の新入社員歓迎式での「燕尾服舞踏会写真」ではない(笑)。「東京拘置所に収監されている松本(麻原)被告の写真」(週刊文春)である。当時マスコミ各社は様々な方法・機材等を駆使して、拘置所から裁判所に移送される松本被告の表情を撮影しようと秘策を巡らしてしていたが、まさか首都高から狙おうとは考えもしなかった。「不肖・宮嶋」と「忍者大倉カメラマン」の2人のフリーランスにマスコミ全社が出し抜かれたわけである。 「不肖・宮嶋」氏がまたしても世間をアッと言わせたスクープ写真が、あの「ズル剥げ金正日」(週刊文春)であった。撮影の際の苦労は宮嶋さんの著書「不肖・宮嶋金正日を狙え!」に詳しく書かれている。金正日をファインダーの中に仕留めた際の「恐怖と興奮」は、オウムに襲われた経験のある僕には同じ報道カメラマンとしてとてもよくわかる。「現場こそわが家、修羅場こそ団欒」。そう言い切る心意気は心から共感できるものだ。ただ違うのは、ロシアの民警に銃口を向けらるような経験をしたことがないということだけれど・・。 その「不肖・宮嶋 金正日を狙え!」のあとがきで、宮嶋さんは次のように書いている。「私は蓮池さんの名も地村さんの名も知らずにいた。つまり、私も拉致事件解決のために屁のツッパリにもならなかった人間の一人であった」と。宮嶋さんの拉致問題に対する懺悔の言葉は、また僕にとっての懺悔の言葉でもある。今でこそこうして「蒼いことばの絆」編集部員に収まってはいるけれど、僕もまた以前は拉致問題に関心を示さなかったマスコミ人の一人だったのだ。拉致被害者のご家族に初めてお会いしたとき、僕はその気持ちを伝えてきた。しかし、ご家族の方はきまって「今、活動をしてくださるそれだけで十分です。気にしないでください、一緒に頑張ってください」と、暖かい言葉をかけてくれるのだ。 拉致問題を知った以上、マスコミ人として目を背けることは許されない。カメラを武器に拉致被害者とそのご家族を支援しようとするそんな宮嶋カメラマンの怒りの言葉がここにある。 |
|||||||||
|
けんた
「蒼い言葉の絆」編集部 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| 先月のこと。『経済産業副大臣室からお電話が入っています』。その知らせに、わたしの会社のオフィスはちょっと騒然となりました。『あの安田がまた何かやらかしたのではないか』。仕事上監督官庁との折衝を行なうことが多いというだけではありません。そもそもわたしがいまの会社に入った経緯というのが、当時の通産大臣がかけた社長宛の直通電話が発端であることを知るわたしの同僚たちは、なんだか怪しいものを見る目つきでわたしを見ています。 わたしは同僚を集めておもむろに答えました。『いやあ。驚かせてごめんね。今度HPで「蒼いことばの絆」という「リレー・コラム」のメルマガを始めたんだ。経済産業副大臣の高市さんに原稿をお願いしたところ。みんなも登録してね』。そしてその場で登録用HPを立ち上げると、次々と同僚を呼びつけては『蒼いことばの絆』のメルマガに半ば強制的に登録させたのでした。 松下政経塾出身。自民党衆議院議員3期目。自民党総務副会長を経ていまや経済産業副大臣。『高市早苗さん』などと『さん付け』で気安く言っていいものかどうかわかりませんが、個人的には高市先生にはとても親近感を持っています。同年代で同じ関西出身というだけでなく、わたしの故郷にある神戸大学ご卒業です(高市先生と直接の面識があることを自慢している高校時代の同級生がわたしにはたくさんいます)。そしてそれ以上に『日本という国を「国家としてあるべき姿」に再構築しよう』という同年代の政治家としての呼びかけとともに、地盤もカバンも看板もないままにその理想のために立候補した高市先生に、これからの日本を変えていく若い政治の力の萌芽を見た思いがしたのでした。その高市先生に原稿をお願いしようというのは、わたしにとってむしろ自然な行動でした。 経済産業副大臣として執務にお忙しい中、快く寄稿を快諾して下さった高市先生は、力強いことばで対北朝鮮政策を語ってくださいました。原稿をお願いしたときにはまだ六ヶ国協議が俎上に上っていない時期であったにもかかわらず、高市先生のことばは六ヶ国協議を見越していたかのような視線で貫かれています。わたしは、高市先生に原稿をお願いした編集部の見識を自慢したいと思います。高市先生のことばをどうぞお読みください。 |
|||||||||
|
安田隆之
「蒼い言葉の絆」編集部 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| 勝谷誠彦さんの『家族』書評をアップしようとしていたその時、蓮池祐木子さんのご母堂、奥土シズエさんの訃報が舞い込んだ。シズエさんは、北朝鮮に拉致されていた24年間、自宅2階にある祐木子さんの部屋を、「いつ戻ってきてもいいように」と毎日、掃除し続けていた。そして、昨年10月17日、祐木子さんを迎えて四半世紀振りの家族団らんのひとときを過ごした翌日、シズエさんは入院された。17日は増元正一さんが亡くなった日でもあった。あまりに残酷な時の流れである。 蓮池薫さんのお婆さんが亡くなった時も言われたことだが、「もう少し長生きすればお孫さんの顔を見れたかもしれない」のではない。「もっと早く帰国させることが出来たら」なのだ。 勝谷さんは言う。「折しも夏休みである。親であるあなたは襟をひっつかんででも子供に『家族』を読ませたまえ。」 「家族」をお読みになってのお便りをお待ちしています。書評でも感想文でも形式は問いません。ぜひお送り下さい。政治家の皆さんからの感想文(反省文か)もお待ちしています。 |
|||||||||
|
Y
「蒼い言葉の絆」編集部 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| 手弁当で集まった小さな編集部ですが、もちろんメンバーはわたしひとりではありません。顔付きや体格も含めて「おとなしい」だとか「控え目だ」とか、ましてや「慎み深い」いう表現から最も遠い場所に位置するメンバーばかりが揃っています。ところが、どういうわけか、毎回の「編集後記」を書く段になると、編集部の飲み会のたとえば焼き鳥串の激しい奪い合いとは裏腹に、「おめえが書けよ」「あんたが書いてよ」と、それは優しい譲り合いが始まるのです。 ところが、今回の「編集後記」だけは、珍しくもわたしが「ぜったいにワシに書かせろ」と早くから宣言していました。実はわたしは先々週に一回目の「編集後記」を書いたばっかりです。企画が始まった当初から何回も登場するのはいかがなものかとも思ったのですが、今回はどうして自分が書きたかったのです。なぜなら、今回「蒼いことばの絆」での執筆をお願いしたのは、昨冬の「ニューヨークタイムズ意見広告」でご一緒した有田芳生さんだからです。 有田さんに初めてお会いしたのは、意見広告がきっかけでした。その後幾度もお話をする機会を得ましたが、そのたびに「主義主張を超えて離ればなれにさせられた家族をひとつにしたい」という思いにわたしは強く気持ちを揺さぶられました。とても暖かい心を持った方なのです。有田さんは家族思いの方です。ご自身の日記「醒酔漫録」には、ご家族のことが登場しない日はないといっても過言ではありません。政治的思想的立場を超えて、たくさんのひとびとが意見広告に賛同してくれたのは、それがひとびとに伝わったからだとわたしは思っています。 優しいだけではありません。そのいっぽうで、有田さんのことばには「強い力」があります。もちろん、有田さんは、わたしとは違って決して過激なことばを使っているわけでもなければ、乱暴な表現で文章を綴られているわけでもありません。大量の読書とフィールドスダディに基づいた「コールドマインド」といってもいいでしょうか、有田さんには、バランスの取れた知性と洞察力から生まれる冷静な力があるのです。 有田さんは、オウム事件を初めとするカルト問題に、そして華やかだと思われる芸能人の人生についてたくさんのレポートを書いてこれらました。有田さんの暖かい心と冷静な筆致は鮮やかに登場人物に光を当ててその実像に迫ります。家族に寄せる暖かい心と冷静な力がひとつになって紡がれた有田さんのことば。今回の有田さんのコラムをどうぞお読みください。 |
|||||||||
|
安田隆之
「蒼い言葉の絆」編集部 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| 西村議員とは短い面会でしたが、世間で言われているような感じではありませんでした。部屋には飛行機の模型が並び、笑えば古き良き日本のいたずら坊主を思い出させる。
心から日本人が日本を愛せるように、一人前の国として自立出来るように日々奮闘している笑顔がとても素敵な人でした。 西村議員が引用した「人の命は地球より重い」という福田赳夫元首相の『ことば』は現在無惨にも踏みにじられています。人権派と呼ばれる人々が多用するこのことばを彼ら自らが踏みにじり、拉致問題を右傾化だとして片づけています。誘拐犯の手から人質を救出する事が右傾化なのでしょうか? 北朝鮮の死亡発表を聞いて「めぐみは濃厚な足跡を残した、めぐみを愛してくださってありがとう」と言った横田早紀江さんの『ことば』、「俺は日本を信じる、おまえも日本を信じろ」と言った増元正一さんの『ことば』。これらののことばを踏みにじる事はもう出来ません。皆さんもコラムが紡ぐ『ことば』に耳を傾け、家族や友人と話し合ってください。そして声をあげ続けてください。 |
|||||||||
|
けんた
「蒼い言葉の絆」編集部 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
拉致問題を語るときにわたしには決して忘れることのできない光景があります。5月7日に東京国際フォーラムで開かれた『国民大集会』。会場を十重二十重に取り囲んだ2万人の人波よりも、会場を埋め尽くした6千人のひとびとの熱気よりも、わたしの心を深く揺さぶったもの。それは『来てくださってほんとうにありがとうございました』ということばとともに、聴衆に向かって深々と頭を下げる横田早起江さんを初めとする家族会の皆さんのお姿でした。 心の中でわたしはそのご家族の姿に深く頭を垂れました。なぜなら頭を下げるべきなのはご家族ではありません。拉致問題を放置し続けるに任せた政治家と政府を養ってきたのはわたしたちだからです。拉致問題を知ろうとしなかったのはわたしたちだからです。政治的な主義主張にとらわれることなく、同じ国に住む同胞のために「自分ができること」を、たとえ小さなことからでも拉致被害者とご家族のために始めていこうと誓ったのでした。 この「蒼いことばの絆」は、そんな志を持った仲間との連帯から生まれました。それぞれがそれぞれの得意分野を活かしながら、拉致被害者とご家族のためにできることを始めようと手弁当で集まりました。誰もが普通の市民です。しかし、それぞれが夫であり妻であり父親であり母親であり、そして親を持ち子どもを持つ市民であるからこそ、拉致問題をもう他人事として傍観することはできないという強い思いに駆られたのでした。「無謀」という二文字が頭の片隅をよぎるなか、恐る恐る執筆をお願いした執筆者の皆さんは、ご多忙中にもかかわらずわたしたち素人の試みに対して快く執筆の返事をしてくださいました。 読者の皆さん。「蒼いことばの絆」は「ことばの織りなす力」です。主義主張を超えてわたしたち市民が「自分ができること」を始めるための連帯の絆です。わたしたち「蒼いことばの絆」とともに考えてください。そして「自分ができること」から始めてください。皆さんが「自分ができること」を始めること。わたしたちは「蒼いことばの絆」がその契機となることを願っています。わたしは「ことばの持つ力」を信じます。 |
|||||||||
|
安田隆之
「蒼い言葉の絆」編集部 代表世話人 |
|||||||||