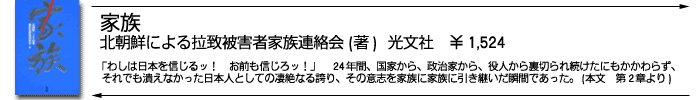|
|
||
| |
2004年2月2日号
|
||
 |
|||
| |
今回のコラムは山際澄夫さんに書いていただきました。著書「拉致の海流 個人も国も売った政治とメディア」は、拉致問題を深く知ろうとした時、先ず手に取った一冊でした。なぜ拉致問題が放置され、何が拉致問題の解決を阻んできたのか。メディアは何を恐れ、何を回避しようとしてきたのか。このコラムとあわせて「拉致の海流」も是非ご一読を。 | ||
| |
|||
|
|||||
|
元米国防総省日本部長のジェームス・アワー氏(バンダービルド大教授)が先ごろ、イラクで死んだ日本人外交官について、「もし私が日本人なら二人の悲劇にいたたまれなくなったに違いないが、同時にこんなに素晴らしい男たちが日本のために働いていたことで胸は誇りでいっぱいになったことだろう」と産経新聞に書いていた。 |
|||||
|
|
|||||
|
山際澄夫(やまぎわ・すみお)
昭和25年、山口県下関市生まれ。ジャーナリスト。 昭和50年、産経新聞に入社し地方支局勤務の後、東京本社政治部で首相官邸、自民党、野党、労働省、外務省の各記者クラブ担当を歴任。平成8年-11年、ニューヨーク支局長。外信部次長などを経て平成14年12月に退社。以後、フリー。著書に「拉致の海流 −個人も国も売った政治とメディア」、「安倍晋三物語」などがある。 公式サイト:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6801/ |
|||||
|
|||||